
定規で線引くの、面倒くさ〜い!
先日、塾で筆算の練習に取り組んだ生徒が言いました。「筆算の線は定規で引きなさい」学校ではそう指導されているようで、塾でもそうしなければいけないと思っていたようです。私は彼女にこう伝えました。

定規を使ったほうがやりやすければ使ってもいいし、使わないほうがやりやすいなら無理に使わなくてもいいよ。色んなやり方を試して、自分がやりやすいやり方を見つけるのが大切だと思うな。
彼女は定規を使わないことを選びました。そして、フリーハンドで丁寧に線を引きながら練習に取り組み、何の問題もなく筆算を解いていきました。
彼女が「面倒くさい」と感じたのは、意義を感じないことを強要されていたからです。定規で線を引く指導には、きっと何らかの狙いがあるのでしょう。もし彼女がその意義を理解し、自らの意思で定規を使っていたのなら、それを「面倒」だと感じることはなかったはずです。
「統制」がもたらすもの
子どもに特定の行動を強要することを「統制」と呼びます。アメやムチを用いて統制すれば、一時的に子どもの行動をコントロールすることができます。しかし、それはあくまで表面的なものに過ぎません。ご褒美をもらうためだったり、怒られるのを避けるために、子どもは仕方なく従うだけなのです。
そして統制を続けても、子どもが心から納得して自ら進んで行動することはまずありません。そればかりか、ずっと統制を続けた結果、子どもとの関係を悪化させてしまったり、子どもの心の健康を損なってしまったりするケースも少なくありません。
ユニセフの2025年の報告書によると、日本の子どもの精神的幸福度は、36カ国中32位だそうです。(2020年の報告では38カ国中37位でした。)この順位の低さには、日本の教育が子どもたちにとって「従わされるもの」になっていることが大きく関係しているのかもしれないと思います。実際、「学校が楽しい!」「勉強が楽しい!」と感じている子どもが少ないのは、非常に残念な現実です。
「自己決定」で子どもは育つ
「面倒くさいなぁ!なぜそうしなければならないの?」
もしもお子様がそんなことを口にするのならば、それは統制を感じていることのサインです。その統制の先にあるのは、身につかない形だけの学習です。そして、これこそが、学習がうまくいかない生徒に共通することなのです。
私たちが目指すのは、子どもたちがしっかり身につく心からの学習ができるよう、育てることです。そしてそのために重要なのが、しっかりと自己決定感を持って学習に取り組めるよう支援することです。
従うことに慣れている子どもは多いですが、自分で決めることに慣れている子どもはとても少ないです。しかし、正しく支援することで、しっかり自分で考え、自分で決めようとするようになります。そして、自分の選択に責任を持ち、力強く行動するようにもなっていきます。
そんなふうに成長していく子どもたちを見ているといつも思います。「自分の行動は自分で決めたい。」きっとそれは、生命としての本能なのだと。お子様にも間違いなく、その本能が備わっています。私たちは、お子様が持てる力を発揮できるよう、お手伝いいたします。
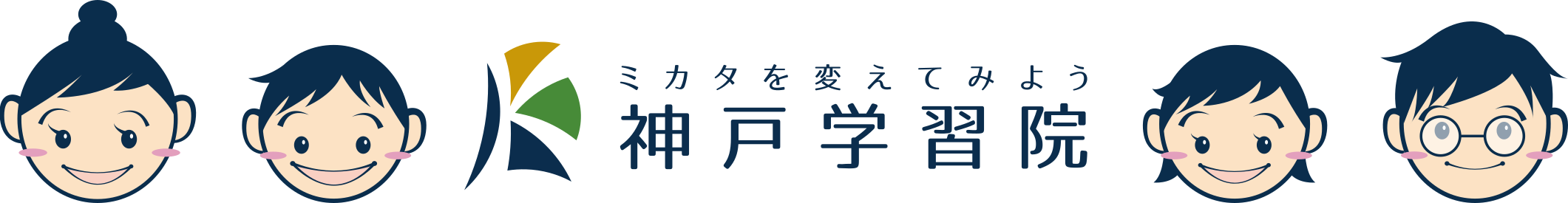





コメント