最近、学習の質がどんどん高まっている中学2年生のSくん。彼は今回の中間テストで、苦手科目を克服する学習法に出会えたようです。Sくんのこれまでのやり方と、成果につながった今回のやり方を紹介します。
理科と社会が苦手なSくん。Sくんはこれまで、知識があやふやであるにもかかわらずワークばかりをやろうとしていました。そして、それではあまりにも分からないからか、教科書から答えを探しながらやってもいました。このようなやり方をするのはSくんばかりではありません、理科や社会が苦手な生徒にとても多く見られます。
理科や社会の学習の基本は、知識をきちんと整理して自在に使えるようにすることです。ところが、いくらワークをやって答えを覚えたところで、知識の整理はなされませんので、成果には繋がりにくいです。ワークをやることで、「勉強している」という安心感は得られるかもしれませんが、肝心の使える知識はあまり得られないのです。
では、知識を整理するにはどうすれば良いのでしょうか?その最も基本的なやり方が、教科書を読むことです。これは、理科や社会の勉強において基本中の基本ですが、それをおろそかにしている中学生は非常に多いです。ですので、理科や社会の勉強方法を尋ねられたら、まずはこのことを伝えます。
ただ、教えても実行する生徒はあまり多くありません。Sくんもまたそうでした。これまで聞かれる度に何度か伝えてはいますが、なかなか実行しようとは思わないようでした。
そんな彼が、今回はとても丁寧に教科書を読み込んでいました。自習室に彼一人しかいない時、自習室からはずっと彼の声がブツブツと聞こえてきました。ただ字面を追うだけではなく、彼は自分に問いかけながら、また自分の言葉に直しながら、丁寧に読み込んでいました。
「ちゃんと理解しているか確かめてください。」彼はそう言って何度も確認にやって来ました。彼が丁寧に読み込んでいることは、よく伝わってきました。単に丸暗記しているのではなく、物事のつながりをきちんと捉えていましたし、周辺資料の内容までもしっかり網羅されていました。
テスト結果は理科も社会も大きく上がりました。これまで平均点の半分ぐらいしかとれないことが多かったのに、今回はどちらも平均点を10点以上上回っていました。大躍進とも言える今回の結果は、間違いなく彼が自分で掴み取った成果です。
では、今回彼が丁寧に教科書を読み込んだのはなぜでしょうか。それは、彼自身が読むと決めたからです。
「しっかり読みなさい!」などと言われて読まされている生徒はまず丁寧に読みません。字面だけ追うような浅い読み方で済ませたり、「読んでも分からへ〜ん」などと言って読まずに済ませようとしたりします。
しかし、読むことを自己決定した生徒は、決してそのようないい加減なことはしません。自分なりに工夫したりアドバイスを求めたりしながら自ら改善し、しっかり読めるように成長していきます。
私たちは彼が納得して自己決定できるよう、支援を続けてきました。それは、「彼にとって成長につながるであろう選択肢を、確かな情報とともに誘導することなく提供すること」であり、「彼がどんな決定をしてその結果どんな失敗をしてしまったとしても、絶対に非難されない安心してチャレンジできる環境を提供すること」であり、そして何より、「彼を操作しようとせずそのままの存在を尊重して受け止めること」です。
そんな支援の中、彼はいろんなことをどんどん自己決定し続け、そして学習の質は上がり続けています。さらに、「勉強が面白い」「自分がこんなに勉強するようになると思わなかった」「塾の日は早く来て勉強することに決めた」など、今までの彼からは想像もつかないような発言がポンポンと飛び出します。
丁寧に学ぶから、しっかり身につく。しっかり身につくから、面白い。面白いから、学習の量が増える。その連鎖反応が今、彼に生じているのだと思います。そして、その連鎖反応の始まりこそが、「自分で決める」なのです。当塾では、このように生徒が自ら学びを深める「自己決定」を何よりも大切にしています。
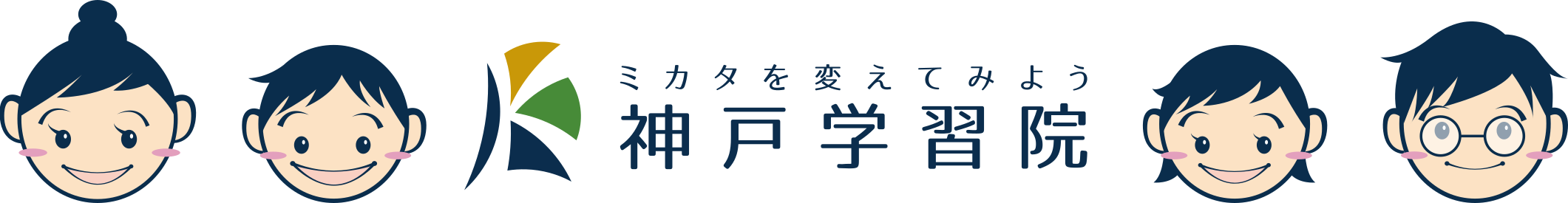

コメント