私たちは毎日、たくさんのことを決めています。今日の夕食から、将来の進路まで。この「決める」という行為は、学習においても非常に重要です。特に、「何を学ぶか」「どうやって学ぶか」を自分で決めることは、学びを深く意味のあるものにするための第一歩です。
ですから、当塾では生徒が自己決定することを大切にしています。「これをしなさい」「こうやってやりなさい」と指示するのではなく、「何を学びたい?」「どんなふうにやってみたい?」と問いかけます。(もちろん、気付きがあればじゃんじゃんアドバイスします。)
ところが学習において、この「自分で決める」ということに、あまり慣れていない生徒が多いなと感じています。先日の夏期講習においてもそれを強く感じました。
今年の夏期講習には、当塾の生徒だけでなく、外部の生徒も複数参加しました。その多くが、やはり自分で決めることに戸惑いを感じたり、何となく選んだりしてしまう傾向にありました。きっと彼らには、学習において自分で決める機会がほとんどないために、意思決定の力が鍛えられていないのだと思います。
これは、エモリー大学のグレッグ・バーンズ博士の研究にも裏付けられています。この研究によると、被験者が自分で決める前に専門家が助言を与えてしまうと、被験者の意思決定を司る脳の中枢がほとんど活動しないことが分かっています。
つまり、教師や親が「これをやりなさい」と指示したり、「こんなふうにやったほうが良い」と先に助言したりすると、子どもは自分で考えず、従うだけになってしまうのです。
一方、普段から自分で決めている生徒たちは、やはりしっかり考えて意思決定しようとします。自分で決めることが当たり前の当塾の生徒たちはもちろんですが、これまで長く学校や塾に通わず自分で勉強を頑張ってきて夏期講習に参加したある生徒も、本当によく考えて決めているなと感じました。彼ら彼女らは、いつも自分で考えて決めてきたために、意思決定の力がしっかり育まれているのだと思います。
意思決定の質は、その後の学習の質に大きく影響します。しっかり考えて決めた生徒は、じっくりと丁寧に学習しようとします。それはきっと、自分で選んだ学習に意義を感じるからなのだと思います。一方、何となく選んだ生徒は、浅く何となく通り過ぎてしまいがちです。
普段の学習において、お子さまが自ら決める機会は十分にありますか?もし、先回りして助言を与えたり、指示ばかりしているのならば、お子さまが自分で考えて行動する力を育む機会を損なっているのかもしれません。
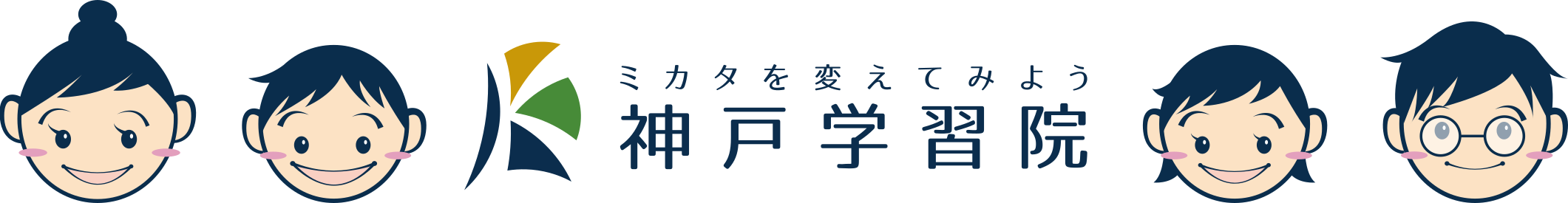



コメント